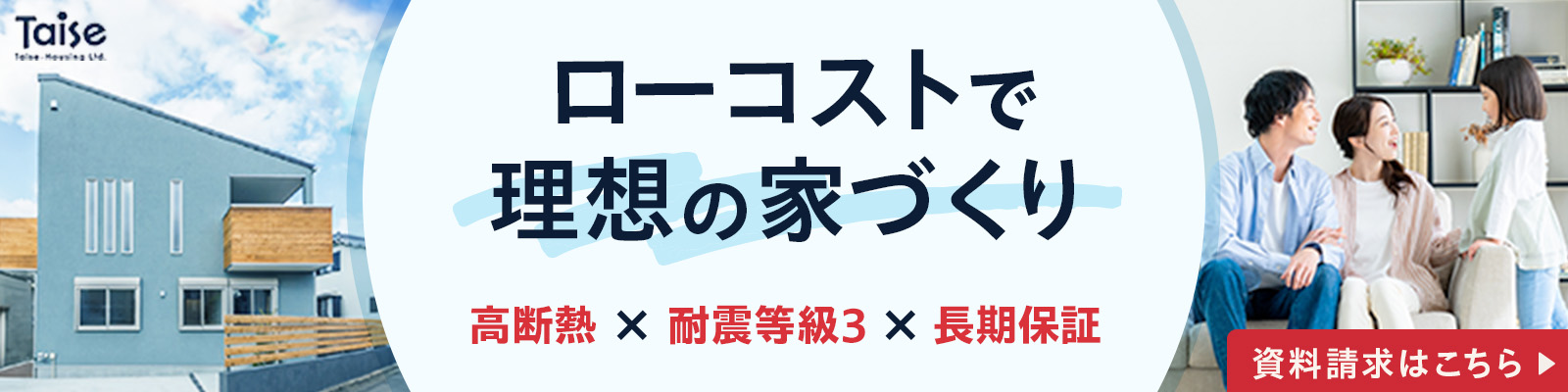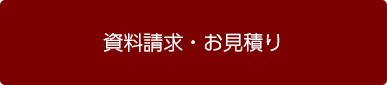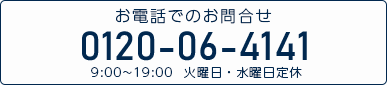注文住宅で予算オーバーする原因
削れるポイントや予算オーバーしない方法を解説
2025/7/4 公開

注文住宅を建てようと家づくりを進めているものの、気付けば予算オーバーになっているケースも多いです。自由度の高い注文住宅だからこそ、こだわりを詰め込み過ぎると費用が膨らんでしまいます。
正しい知識と計画性があれば、予算内で満足いく住まいを建てることは可能です。本記事では、注文住宅で予算オーバーする原因や、費用を抑えられるポイント、逆に費用を抑えると後悔しやすい点などを解説します。注文住宅を建てたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事
土地込み注文住宅を6000万円で建てるなら?費用相場や建築時のポイント
2025/7/4 公開
土地込み注文住宅を5000万円で建てられる?費用シミュレーションや土地・建物の選び方とは
2025/5/31 公開
見積もり相談を無料で承ります。
注文住宅の予算に不安を抱えている方はこちらから
注文住宅で予算オーバーする原因

注文住宅は自由度が高い半面、予算がオーバーするリスクもあります。予算オーバーとなる主な原因を見ていきましょう。
① 資金計画を立てていない
注文住宅で予算オーバーする原因の一つが、資金計画を立てていないことです。間取りやデザインを考える前に、「毎月いくらなら無理なく返済できるか」「何年で住宅ローンの完済を目指すか」といった資金の見通しを立てるのが大切です。
その際には「年収倍率」「返済負担率」という2つの指標を活用します。年収倍率とは、住宅購入にかかる費用を世帯年収で割った数値で、数値が大きくなるほどリスクも高まります。住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査」によると、2023年度における年収倍率の平均は、土地付き注文住宅が7.6倍、注文住宅が7.0倍でした(※)。
返済負担率とは、年収に占める年間ローン返済額の割合です。金融機関が融資を判断する際の目安にもなっており、一般的には30〜35%が目安とされています。ただし、家計への負担を考えると、手取り収入の20〜25%に抑えるのが理想です。事前に年収倍率と返済負担率のシミュレーションをして、堅実な資金計画を立てるようにしましょう。
参考:住宅金融支援機構.「2023年度フラット35利用者調査」(参照 2025-06-01)
② 優先順位をつけていない
注文住宅は間取りや設備、内装などを自由に選べるのが魅力です。しかし選択肢が多い分、あれもこれもと希望を盛り込むうちに、気付けば予算を大幅にオーバーしてしまうこともあるでしょう。
そのため、初期段階で「譲れないもの」と「妥協できるもの」の優先順位を明確にしておくことが大切です。優先順位がつけられていないと、判断に迷って全て盛り込んでしまい、時間もお金も浪費してしまう可能性があります。
③ 附帯工事費や諸費用を計算していない
注文住宅の費用といえば、まずは本体工事費を思い浮かべやすいですが、他にも費用は発生します。代表的なのが附帯工事費と諸費用です。
附帯工事には、古家の解体や地盤改良、屋外給排水工事、造成、整地、屋外電気工事などが含まれ、土地の状態によって工事内容や費用が変動します。
諸費用には、住宅ローンを利用する際にかかる事務手数料、登記費用(所有権移転登記や抵当権設定登記)、不動産会社に支払う仲介手数料などが含まれます。
これらの費用を事前に見積もらず、建物本体の価格しか考えていないと、最終的に予算オーバーにつながってしまうでしょう。
④ 外構計画を事前にしていなかった
注文住宅では、外構計画は後回しにされることもあります。後からブロック塀やウッドデッキの設置などを追加すると、予想以上に費用がかさんでしまい、結果として予算オーバーに陥るケースもあるのです。
外構も住まいの一部として重要な要素であり、コストも安くありません。本体工事や間取りの設計段階から外構の計画も並行して進めておくことが大切です。
注文住宅の費用で予算を削れるところ
注文住宅では、全ての要素でこだわろうとすると予算が膨らんでしまいます。希望を実現しながらも予算内で抑えるためには、どこで予算を削るかの見極めが大切です。ここからは、土地や間取り、外観など、予算を抑えるポイントを解説します。
① 土地
土地にかかる費用は、土地代だけではありません。土地に関する主な費用は、以下の通りです。
<土地に関する主な費用>
| 項目 | 費用を削るポイント・注意点 |
|---|---|
| 土地代 | どこに注文住宅を建てたいか、希望するエリアを広げるのが費用を削るコツ 駅から少し離れた場所や、急行が停まらない駅周辺、変形地・北側道路の土地などを選ぶと価格を抑えられる |
| 地盤改良費 | 購入前の調査は難しい場合もあるものの、専門家に相談すればある程度、費用のシミュレーションが可能 |
| 解体工事費 | 古屋付きの土地では、解体費用が数百万円かかることもある |
| 水道・ガス管引き込み工事費 | 引き込む距離や経路で費用が変わる |
土地代は大きな出費であるからこそ、その選び方次第で全体の予算に大きく影響します。予算を踏まえて、しっかり検討しましょう。
② 間取り・延床面積
間取りや延床面積を工夫することによって、費用を抑えられます。例えば、廊下や玄関ホール、個室の面積をコンパクトにすれば、全体の面積が減り、建築費用の削減につながります。
リビング階段を採用したり、収納スペースを必要最小限にしたりするなどの工夫をすれば、狭さを感じることなく快適な空間を確保できるでしょう。また水回りを近くにまとめれば、必要な配管を抑えられるため工事費用や材料費を抑えることも可能です。
③ 外観
外観のデザインも建築費用に影響します。例えば、1階と2階の床面積や外壁ラインがほぼ同じ「総二階」の家にすればコストを抑えられます。建物の凹凸が少なくなるため、構造が安定し、耐震性も向上しやすいでしょう。
また、屋根もシンプルな形状にすることで、材料費や施工費が抑えられ、全体のコストダウンにつながります。外観に過度な装飾を盛り込まないことが、費用を抑えて家づくりをする際のポイントです。
④ 内装
内装には、費用を調整しやすいポイントが多数あります。例えば、壁紙はデザイン性の高いグレードのものを避け、シンプルなものにするだけでコストを抑えやすいです。また床材も、無垢材から合板に変えることで節約できる可能性があります。
さらに照明はインターネットでなるべく安いものを購入したり、建具はグレードを抑えたりすると、予算を抑えられるでしょう。
⑤ 住宅設備
住宅設備にはつい最新の機能を取り入れたくなりますが、あれこれ追加していくうちに予算オーバーになりやすいので注意が必要です。実際に住み始めてから「必要なかった」と感じて後悔するケースもあるため、本当に必要なものを見極めることが大切です。
<住宅設備の費用を抑える例>
| 項目 | 費用を削るポイント・注意点 |
|---|---|
| 水回りのグレードを下げる | 見た目よりも機能性を重視する |
| 太陽光発電システムの導入 | 太陽光発電システムを導入する場合としない場合で、初期費用と毎月の電気代にどの程度違いが出るのかを確認する |
| 食洗機の必要性を検討 | 家族構成やライフスタイルによっては不要な場合もある |
予算と使い勝手のバランスを考えながら、費用をかけるべきかどうかを検討しましょう。
⑥ 外構
外構も、工夫次第で費用の削減が可能です。
例えば、フェンスやブロック塀ではなく、オープン外構やセミクローズ外構にすると節約しやすいでしょう。
オープン外構とは敷地を囲う塀やフェンスを設けず、開放的な造りにする外構スタイルです。セミクローズ外構とは道路側など一部に塀やフェンスを設けるスタイルで、プライバシーや防犯面にも配慮しつつもコストを抑えられます。
費用と暮らしの快適さ、防犯面のバランスを意識して外溝計画を立てましょう。
⑦ 住宅ローンの諸費用
住宅ローンを組む際は、金利だけではなく諸費用も必要です。諸費用の金額や内容は金融機関によって異なるため、複数の金融機関や返済プランを比較検討しましょう。
住宅ローンを利用する際に必要な事務手数料には定率型と定額型があり、一般的に採用されているのは定率型です。例えば、定率型の事務手数料は借入金額の2%程度が相場とされますが、定額型の場合は3万~5万円程度に抑えられるケースもあります。ただし、定額型の場合、保証料が必要になる場合もあるので注意しましょう。保証料とは、保証会社が保証人になるための費用です。一括前払いの他、金利に0.2%程度を上乗せして支払う方法もあります。
この他、印紙代や団体信用生命保険料なども発生し、諸費用全体としては購入価格の3~6%が目安となります。
なお、注文住宅の場合、着工時と完成時に費用を分割して支払うことが一般的です。分割融資やつなぎ融資を利用する際には、それぞれの金利や手数料を確認しておきましょう。分割融資では1本の住宅ローンで複数回に分けて資金を受け取れるのに対し、つなぎ融資では住宅ローンとは別に短期の融資契約が必要となります。分割融資は金利が低い傾向にあるものの、融資の度に手数料などがかかります。つなぎ融資は金利が高いものの、手数料は安く抑えられることが一般的です。
注文住宅で予算を削って後悔するところ

注文住宅では予算を抑える工夫も大切ですが、削り過ぎると後悔するケースがあります。暮らしの快適さや安全性に関わる部分は、コストよりも質を重視するのが大切です。ここからは、コストを削って後悔しやすいところをご紹介します。
① 優先順位の高いもの
優先順位の高い間取りや設備にかける予算は削らないようにしましょう。例えば「家族が長時間集まるリビングが狭過ぎて、不便」「客間を用意するべきだった」などと、暮らし始めてから後悔する可能性もあります。特に間取りは完成後の変更が難しいだけに、優先順位の高い部分についてはしっかりと検討するようにしましょう。
② 気密性・断熱性
気密性と断熱性は、注文住宅で重視すべきポイントです。気密性と断熱性が低い住宅だと、夏は暑く冬は寒くなりやすく、エアコンや暖房器具に頼る生活になってしまいます。
光熱費がかさむだけでなく、室内の温度差によってヒートショックが起きるリスクも高まります。特にヒートショックは命に関わることもあるため、気密性と断熱性の高い住宅設計を目指しましょう。
③ 防犯性
防犯性を高める設備設置も、しっかり予算をかけておきたいポイントです。例えば、強化ガラスやセンサーライト、監視カメラなどを設置していれば、万が一のときに備えられます。予算を抑えるために削るのは、おすすめできません。
④ 収納
予算を抑えたいからといって、収納スペースを安易に省かないようにしましょう。収納が足りないと、家の中に物があふれて散らかりやすくなり、どこに何があるか分からなくなる可能性もあります。場合によっては同じ物を再度買ってしまうこともあるでしょう。
収納は多ければ良いというものではありません。使いにくい場所や不要なスペースが増えると逆に不便になるため、必要な量を必要な場所に収められるよう、計画的に収納スペースを配置しましょう。
⑤ 外壁材や屋根材
外壁材や屋根材を安さだけで選ぶと、初期費用は抑えられても長い目で見ると負担が増えることがあります。安価な素材は耐久性が低く、寿命も短いため、早期にメンテナンスやリフォームが必要になることもあるのです。
結果としてトータルコストがかさんでしまうため、外装は一定以上の品質のものを選ぶようにしましょう。将来の修理費用やメンテナンスコストを抑えられます。
注文住宅で予算オーバーしないためには
ここからは注文住宅を建てるに当たって、予算オーバーしないためのポイントをご紹介します。
① 資金計画を立てる
注文住宅を建てる際に最初に行うべきなのは、資金計画の立案です。毎月いくらまでなら無理なく住宅ローンを返済できるのか、何年で完済したいのかをシミュレーションすると、自身や家族に合った予算が明確になります。
予算がオーバーする可能性も踏まえて、最初は少なめの金額で計画を立てておくのもおすすめです。
② 優先順位をつける
注文住宅では、予算内に全ての希望を叶えるのは難しいため、優先順位をつけることが大切です。まずは自身やご家族が求める内容を全て書き出してから、「どうしても叶えたいこと」「できれば叶えたいこと」「叶わなくてもよいこと」に分類しましょう。
優先順位を明確にすることで、予算オーバーしそうになったときも何を盛り込んで何を削るべきなのかを冷静に選択でき、満足度の高い家づくりができます。
③ 制度や補助金を利用する
注文住宅を建てる際には、さまざまな制度や補助金を利用することで費用の負担を軽減できます。家づくりで活用できる制度や補助金としては、住宅ローン減税や各種税金の優遇措置、省エネ住宅向けの補助金などがあります。住んでいる場所や条件によっても利用できる制度や補助金は異なるため、行政のホームページやハウスメーカーのWebサイトなどで事前に確認しておきましょう。
④ 複数の会社を比較する
注文住宅は会社によって、坪単価や附帯工事費、構造、間取りの自由度、設備・内装の仕様などが異なります。同じ予算でも提案内容に差が出るため、複数社を比較して自身に合った会社に依頼するのがおすすめです。
なお、比較する会社が多過ぎると時間がかかる上にどこに依頼するか判断が難しくなるため、3社ほどに絞って比較検討しましょう。
タイセーハウジングの資金相談
750棟以上の注文住宅の提供実績のあるタイセーハウジングでは、専門のマネーコンサルによる資金相談を実施しています。土地代や建築費だけではなく、諸費用まで含めた総額を明確に提示し、顧客それぞれに丁寧に説明。顧客の要望や状況に適した資金計画をご提案します。
注文住宅を建てた後も、金利や条件の見直しが必要になった際には、借り換えの提案や将来を見据えたアドバイスも可能です。
予算内で素敵な注文住宅を建てよう!
注文住宅は自由度が高いだけに、予算オーバーしてしまうリスクも高くなります。予算内に抑えつつ、快適な住まいを実現するには、資金計画や優先順位の整理、制度や補助金の活用、複数社の比較検討など、計画的に準備をしておくことが大切です。
タイセーハウジングでは、資金計画はもちろん、土地探しから設計・施工・アフターフォローまでをワンストップでサポートしています。土地のみの相談や、建物・資金に関するご相談も専門スタッフが丁寧に対応します。「注文住宅を建てたいけど、何から始めればいいか分からない」「予算内に納めつつ、希望を叶えたい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
各種カタログや施工事例集のご請求・お見積りをご希望の方は、こちらのフォームにて承っています。
資料請求・お見積り | タイセーハウジング株式会社
ご相談はZOOM(ズーム)でも無料で受け付けています。ぜひお気軽にお申し込みください。
無料相談(来店 or オンライン) | タイセーハウジング株式会社