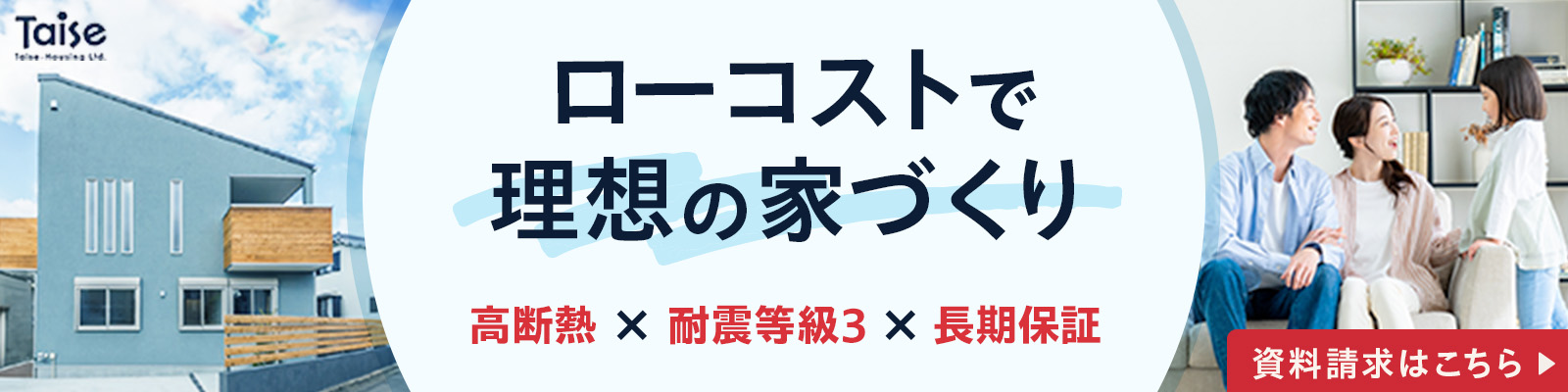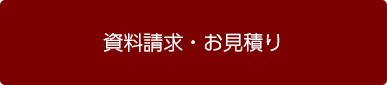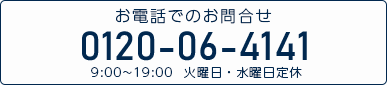長期優良住宅は取得すべき?
メリット・デメリットや手続き方法などを徹底解説
2024/9/14 公開

長期優良住宅とは、国の長期優良住宅認定制度の基準を満たした住宅のことです。認定されると税金面や住宅ローンの金利優遇など、さまざまな恩恵を受けられます。これから家を買いたい方や建てたい方、長く快適に暮らしたい家を探している方におすすめです。
一方、長期優良住宅には、建築する際に通常よりコストがかかったり、認定までの手続きが面倒だったりするデメリットもあります。
そこでこの記事では、長期優良住宅のメリットとデメリット、手続き方法を解説します。最後まで読むことで、長期優良住宅を取得するべきかを判断できるようになりますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事
高気密・高断熱住宅がヒートショック対策になる理由|場所別の予防方法も解説
2025/7/4 公開
注文住宅に耐震等級3は必要?注文住宅で耐震性を高めるメリットと注意点を解説
2024/12/16 公開
設計相談を無料で承ります。
長期優良住宅の基準を満たした注文住宅を建てたい方はこちらから
長期優良住宅とは?

長期優良住宅は長く良好な状態で使用できる優れた住宅です。ここでは、長期優良住宅の概要や認定基準について説明します。
① 長期優良住宅とは「長く安心して住み続けられる住宅」のこと
長期優良住宅とは、2009年(平成21年)に施行された国の認定制度の基準を満たした住宅のことです。この制度が始まった背景には、日本の住宅事情における「スクラップ&ビルド」を抑制することにあります。住宅を建てては壊すという循環を改め、質の高い建物を建築し、適切な手入れをしながら長く住み続けられる住宅の普及を目指したものです。
認定されると住宅ローン減税で優遇されたり、不動産取得税の軽減を受けられたりと、さまざまなメリットがあるのが特徴です。一方で認定を受けるには、劣化を防ぐ対策や耐震性能など、多くの基準を満たす必要があります。手間やコストがかかる他、間取りの制限や定期的なメンテナンスの必要性など一定の負担も求められます。
② 長期優良住宅の主な認定基準
長期優良住宅の認定を受けるには、さまざまな基準を満たす必要があります。主な基準は以下の8つです。
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 省エネルギー対策
- 住戸面積
- 居住環境
- 維持保全計画
- 災害配慮
それぞれの基準を説明します。
劣化対策
長期優良住宅の基準として、数世代にわたって居住できる構造躯体が使用されていることが挙げられます。具体的には、住宅性能表示制度で定められた劣化対策等級(構造躯体等)が、最高の3に該当していることが条件です。等級3とは、75〜90年使える耐久性を確保できるレベルの住宅です。
耐震性
極めてまれに発生する地震があった際にも住み続けられるよう、改修できるレベルの損傷に抑えることを目指した基準です。具体的には、地震に対する強度を示す耐震等級が2(階数が2以下の木造住宅で、壁量基準による場合は3)に当たる住宅などが認定条件となっています。
維持管理・更新の容易性
構造躯体より劣化が早い給排水やガスなどの設備配管について、点検や清掃、補修、更新を容易にする措置が講じられていることが基準となります。住宅性能表示制度における維持管理対策等級(専用配管)3が基準です。
省エネルギー対策
建物の断熱性能や、エネルギー消費量の削減度合いを示す基準です。住宅性能表示制度の断熱等性能等級が5かつ、一次エネルギー消費量等級が6であることが基準となります。
住戸面積
良好な居住空間を確保するため、必要な規模を有するかどうかを判断します。戸建て住宅の場合は75平方メートル以上で、少なくとも一つの階の床面積が40平方メートル以上あることが条件です。
居住環境
地域における居住環境の維持・向上に配慮されている必要性などを求めた基準です。地区計画や景観計画、条例、建築協定、景観協定などの区域にある場合は、その内容に沿ったものであることが求められます。
維持保全計画
将来を見据えて住宅を長く使用するために、次の項目について定期的な点検・補修などを行う計画が定められている必要があります。
- 構造耐力上の主要部分
- 雨水の浸入を防止する部分
- 給水または排水のための設備
災害配慮
自然災害が発生する危険性のある地域においては、リスクの高さに応じて、所在地域の自治体が定めた措置を講じる必要があります。
長期優良住宅を取得するメリット

長期優良住宅には、さまざまなメリットがあります。税金や住宅ローンの金利優遇といったメリットだけでなく、住まいの価値も高められる点もポイントです。ここでは、長期優良住宅を取得することで得られる主な利点を解説します。
① 税金の特例措置が受けられる
長期優良住宅の認定を受けると、次のような税制優遇措置を受けられます。
- 住宅ローン減税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 固定資産税
- 投資型減税
- 贈与税
以上の特例は、住宅取得時の負担を軽減し、質の高い住宅の普及を促進する目的から設けられたものです。それぞれの内容や適用条件を解説します。
住宅ローン減税
税の特例措置としては、まず住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の優遇が挙げられます。住宅ローン減税は、新築住宅を購入または建築し、2025年末までに入居した場合、年末のローン残高の0.7%を13年間にわたって所得税から控除できる制度です。
例えば、年末のローン残高が4,000万円なら、その0.7%に当たる28万円が控除されます。所得税から控除しきれない部分がある場合は翌年の住民税から控除されます。
控除対象となる借入限度額は住宅性能により異なり、長期優良住宅の認定を受けている新築住宅のケースが4,500万円と最大です。以下、ZEH水準省エネ住宅が3,500万円、省エネ基準適合住宅が3,000万円と続きます。
なお、原則として省エネ基準を満たさない住宅は減税の対象外です。ただしその場合でも、2023年末までに建築確認を受けて2025年末までに入居する場合は、借入限度額2000万円、控除期間10年で住宅ローン減税が適用対象となります。
※出典:国土交通省.「住宅ローン減税」.(2024-08-04).
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を購入または建築した際にかかる税金です。通常、新築住宅の場合、建物部分は次の式で計算できます。
建物の不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 1,200万円) × 税率3%
つまり、固定資産税評価額が1,200万円以下の住宅であれば、不動産取得税はかかりません。
また長期優良住宅の基準で2026年3月31日までに新築を建てた場合、1,200万円の控除が1,300万円に拡大されます。適用条件は、都道府県のルールに従って申告をすること、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることです。
例えば、建物評価額が3,000万円の家を新築した場合、通常は下記のように54万円の不動産取得税がかかります。
建物の不動産取得税 = (3,000万円 - 1,200万円) × 3% = 54万円
これが長期優良住宅の場合は、次の式のように51万円となり、3万円の節税効果が得られます。
建物の不動産取得税 = (3,000万円 - 1,300万円) × 3% = 51万円
※出典:国土交通省.「認定長期優良住宅に関する特例措置」.(2024-08-04).
登録免許税
住宅を取得した場合、新築したなら所有権保存登記を、登記されている物件を取得したなら所有権移転登記を行う必要があります。登録免許税は、この登記を行う際に必要な税金で、固定資産税評価額に税率をかけて計算するのが原則です。
新築・未入居の長期優良住宅を取得する場合、この税率が優遇されます。一般の住宅では保存登記が0.15%、移転登記が0.3%のところ、長期優良住宅の保存登記は0.1%、移転登記は0.2%(マンションは0.1%)となります。
優遇措置の適用を受けるには、取得した方が住むことや、1年以内に登記をすること、床面積50平方メートル以上であることが条件です。
※出典:国土交通省.「認定長期優良住宅に関する特例措置」.(2024-08-04)
固定資産税
固定資産税は、不動産を所有している人が毎年市町村に納める税金です。新築の戸建て住宅を購入または建築した場合、通常は3年間にわたって税額が2分の1に軽減されます。
長期優良住宅の認定を受ければ、この軽減期間が5年間に延長されます。適用を受けるには、2026年3月31日までに新築された住宅で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが条件です。
※出典:国土交通省.「認定長期優良住宅に関する特例措置」.(2024-08-04).
投資型減税
投資型減税(認定住宅等新築等特別税額控除)とは住宅ローンを利用せず、現金で購入した場合に利用できる制度で、2024年1月1日から2025年12月31日までに入居した長期優良住宅の所有者が対象となる税制優遇措置です。
新築または未使用の長期優良住宅に居住する場合、長期優良住宅の基準を満たすためにかかった費用(かかり増し費用)の10%相当額を、その年の所得税から控除できます。控除しきれない金額は翌年に繰り越すことが可能です。
かかり増し費用は、4万5,300円に住宅の床面積をかけて算出します。かかり増し費用の上限は650万円となっているため、控除額の上限はその10%に当たる65万円です。住宅ローン減税との併用はできない他、最大13年間控除できる住宅ローン減税と異なり、投資型減税は1回しか利用できません。
※出典:国土交通省.「認定長期優良住宅に関する特例措置」.(2024-08-04)
贈与税
住宅を取得する際に父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合に、一定額までの贈与について贈与税が非課税になる制度があります。非課税となる限度額は、一般住宅の場合は500万円ですが、「質の高い住宅」は1,000万円まで引き上げられます。この条件に該当するのが、長期優良住宅です。
床面積50平方メートル以上(所得金額1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)の住宅の資金について、2026年12月31日までに贈与を受けた場合などが対象となります。
※出典:国土交通省.「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」.(2024-08-04).
② 住宅ローンの金利優遇を受けられる
長期優良住宅を取得すると、住宅ローンの金利優遇措置を受けられます。最長35年間、固定金利が適用されるフラット35で、長期優良住宅を取得すると適用されるのが【フラット35】維持保全型と【フラット35】S(金利Aプラン)です。維持保全型は当初5年間0.25%、S(金利Aプラン)は当初5年間0.5%金利が引き下げられ、併用によって当初5年間の金利は合計0.75%下がります。
【フラット35】S(金利Aプラン)よりも省エネルギー性、耐震性などでさらに質の高い住宅が対象になる【フラット35】S(ZEH)だと、当初5年間の金利は0.75%下がります。この場合、維持保全型と組み合わせることで、当初5年間の金利は合計1%下がります。
※出典:住宅金融支援機構.「フラット35」.(2024-08-04)
③ 地震保険料の割引がある
長期優良住宅の認定を受けると、地震保険料の割引を受けられます。割引率は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく耐震性能によって異なり、最高レベルの耐震等級3と免震建築物は50%です。耐震等級2は30%、耐震等級1は10%の割引率となります。
割引を適用するには、認定通知書や技術的審査適合証など長期優良住宅に関する証明書類を保険会社に提出し、耐震レベルなどが確認される必要があります。証明書類がないと割引を受けられないため、書類は大切に保管しておきましょう。
※出典:日本損害保険協会.「損害保険Q&A」.(2024-08-04)
④ 補助金を受けられる
長期優良住宅を新築すると、国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」の補助対象となります。2005年4月2日以降に生まれた子を持つ家庭、または夫婦のいずれかが1983年4月2日以降に生まれたことが条件です。支援事業に登録をしたエコホーム支援事業者と工事請負契約を結ぶことも必須になっています。
補助額は1戸当たり最大100万円です。申請時(2024年12月末まで)に基礎工事が完了している必要がある他、補助の予算が上限に達した場合はその時点で終了します。
※出典:国土交通省.「子育てエコホーム支援事業」.(2024-08-04)
⑤ 長く住み続けられる
長期優良住宅は、高い断熱性能と耐震性能を備えていることが大きなメリットです。夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を実現し、地震時にも建物の損傷を最小限に抑えられます。
こうした性能の高さは、長期にわたって安心して快適に住み続けられることにつながります。建物の寿命が大幅に延びれば、次の世代へと住まいを引き継ぐことも可能です。長期優良住宅は、世代を超えて使い続けられる家族の資産にもなるでしょう。
⑥ 資産価値が高くなる
長期優良住宅の認定を受けることで住宅の価値が高まり、将来的な資産性にプラスの影響を与えます。例えば将来、家を売却することになった際、「長期優良住宅の家」という点がアピールポイントとなるでしょう。
高品質で長期的な安心感が保証された住宅であることが、購入を検討する人の高評価につながることが期待できます。
長期優良住宅を取得するデメリット
長期優良住宅には多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットもあります。ここでは、長期優良住宅の取得を検討する際に考慮すべき主なデメリットを解説します。
① 申請するのに時間と費用がかかる
長期優良住宅を取得する際のデメリットには、申請手続きの煩雑さがあります。申請は住宅の着工前に行う必要があり、通常より1週間〜1カ月ほど時間がかかります。場合によっては審査に必要な書類の準備や作成に時間を要し、さらに長期化することも考慮しなければなりません。
申請には費用も必要です。まず、県や市などの所管行政庁に支払う認定申請手数料がかかります。自治体によって異なりますが、手数料に建築会社に申請手続きを代行してもらう費用も含めると、20万〜30万円の出費が必要でしょう。建築会社によって代行手数料が異なるため、複数の会社に確認することをおすすめします。
② 建築コストが高くなる
長期優良住宅の認定を受けるには、長く安全に暮らせる住宅を実現する必要があるため、国が定めた高い性能基準を満たさなければいけません。基準を満たすために、通常の住宅よりもグレードの高い良質な構造材や設備を使用する必要があります。
一般的な住宅より高性能な断熱材や耐震構造などが求められ、結果として、建築コストが通常よりも上昇していきます。ただし、建築コストをかけて高性能な住宅を建てることで維持費が抑えられ、長期的にはコストを削減できるでしょう。
③ 間取りの制限を受ける
長期優良住宅の認定を受けるには一定の基準を満たす必要があり、これが間取りに制限をかけるケースが考えられます。特に耐震性の基準を満たすために、壁や柱の配置に制約が生じることもあるでしょう。柱や壁を減らして広々とした空間にする設計は住宅の魅力を高めますが、耐震性との両立が難しいこともあります。広い間口の窓の設置、スキップフロアの採用なども制約を受けます。
長期優良住宅を検討する際は、希望する間取りと認定基準の整合性について、設計士とよく相談しながら慎重に検討することが重要です。
④ 建築後に定期的なメンテナンスや点検が必要
長期優良住宅の所有者には、定期的なメンテナンスや点検が求められます。認定基準には維持保全も含まれ、30年以上の期間、10年以内の間隔で定期的に点検を行うことが定められています。
点検やメンテナンスを怠ると、長期優良住宅の認定を失う可能性があるため注意が必要です。場合によっては、補助金や減税された税金の返還を求められるケースもあります。維持管理は住宅の長寿命化と性能維持のために不可欠ですが、所有者にとっては負担になるかもしれません。
※出典:住宅性能評価・表示協会.「長期優良住宅にお住いの方へ」.(2024-04-01)
長期優良住宅認定を受けるための手続きの流れ
長期優良住宅の認定を受ける際、多くのケースではハウスメーカーや工務店の担当者が手続きを代行してくれます。しかし、手数料で費用が増加するため、費用を抑えたい場合は自ら手続きを行うことも可能です。自力で行う場合は資料の準備や不備などで時間がかかることから、どちらの方法を選ぶかは慎重に検討する必要があります。
ここでは、長期優良住宅の認定を受けるための具体的な手続きの流れを紹介します。自分で行うか代行を依頼するか、より適切に判断するための参考にしてください。
① 技術的審査を受ける
長期優良住宅の認定を受けるには、住宅が認定基準を満たしているかどうかを確認する「技術的審査」を受ける必要があります。
建築主や建築会社の担当者が、登録住宅性能評価機関に必要書類を提出します。提出書類には、設計住宅性能評価申請書または確認申請書に加え、設計内容説明書、各種図面、計算書などの添付図書が含まれます。
② 確認書などの交付を受ける
次に確認書等の交付を受けます。確認書等とは「確認書」または「住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認結果が記載されたもの)」のことです。登録住宅性能評価機関が提出書類を精査し、建物が長期優良住宅の基準を満たしているか技術的審査を行った上で確認書等を交付します。
③ 認定申請を行う
確認書などの交付を受けたら、建築主または建築会社の担当者が所管行政庁に認定申請を行います。申請の際は認定申請書と共に、確認書等や各種図面、さらに所管行政庁が求める追加書類が添付図書として必要です。申請後、所管行政庁による適合審査が行われ、認定基準を満たしているかが最終的に判断されます。
④ 認定通知書の交付を受ける
所管行政庁による適合審査に合格すると、長期優良住宅の認定通知書が交付されます。認定通知書が交付される前でも、認定申請を行っていれば着工は可能で、着工後に認定を受けられます。
安心で住みやすい家を建てよう
長期優良住宅を選ぶと、快適に長く暮らせる安心な住まいを取得できます。ただし、認定までの手続きは煩雑です。慣れていないと申請に不備があり、余計な時間がかかってしまうこともあるでしょう。長期優良住宅の認定を受けつつ、希望の間取りを実現するにはプロの視点も不可欠です。申請を希望する場合や、長期優良住宅に関心がある場合は、手続きに慣れている建築会社に依頼することをおすすめします。
タイセーハウジングは2009年から、神奈川県厚木市と東京都世田谷区を拠点に注文住宅を手がけてきました。お客さまの理想をカタチにすることを心がけ、地域密着の工務店としてこれまでに1,000棟以上の住まいを提供しています。長期優良住宅の取得で不安や疑問がある方は、認定手続きの実績もあるタイセーハウジングにぜひ一度ご相談ください。