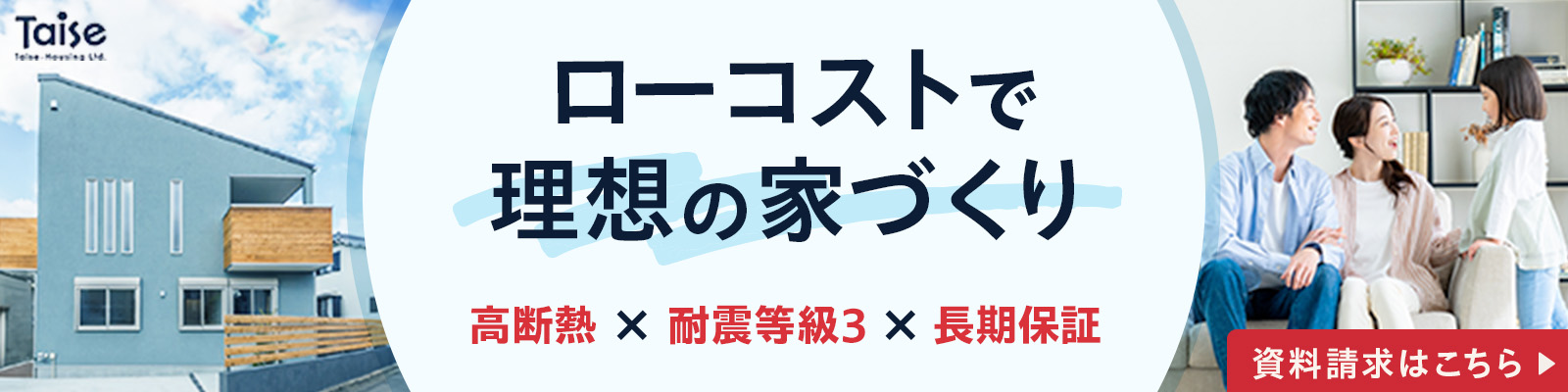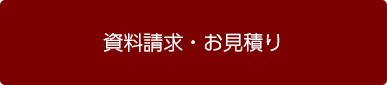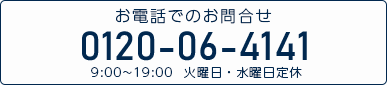注文住宅に耐震等級3は必要?
注文住宅で耐震性を高めるメリットと注意点を解説
2024/12/16 公開

地震など災害の多い日本では、耐震性の高い家を建てることは非常に重要です。耐震性が高いといわれる「耐震等級3」の住宅を検討する方もいますが、果たしてそこまでの耐震性が本当に必要なのでしょうか?
この記事では、耐震等級の基本や確認すべき4つのポイント、耐震等級3を取得するメリットとデメリット、注意点について詳しく解説します。さらに、信頼できるハウスメーカーや工務店の選び方にも触れますので、注文住宅で安心して暮らせる住まいをお考えの方はぜひ参考にしてください。
設計相談を無料で承ります。
地震に強い注文住宅を建てたい方はこちらから
耐震等級とは

耐震等級とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、住宅の耐震性能を3段階で示す指標です。
地震に対する建物の強さを数値化し、視覚的にわかりやすく示すことで、住宅購入者が「この住宅がどの程度の耐震性能を備えているか」を把握できるようになっています。耐震等級は、住宅の安全性を客観的に判断する基準として役立っており、安心して住宅を選ぶための重要な指針となっています。
それに対して、よく耳にする「耐震基準」というのは、建築基準法により定められた最低限の耐震性能で、建物が地震に耐えられるために必要な基準です。耐震基準は全ての建物に義務化されていますが、耐震等級は必須ではなく、建築主が任意で選択することとされています。耐震基準が最低限の基準であるのに対し、耐震等級はより高い安全性を求める際に参考にできる基準ということです。
次に、耐震等級1から3までの具体的な違いについて詳しく見ていきましょう。
① 耐震等級1
耐震等級1は、建築基準法が定める最も低いランクの耐震性能を示します。この等級で求められているのは、震度5程度の地震で損壊せず、震度6強から7の地震でも一度は耐えられる程度の耐震性能です。しかし、大規模地震発生後は、倒壊や崩壊を防ぐための大規模な修繕や住み替えが必要になる可能性があります。
耐震等級1を満たすためには、2000年以降に施行された現行の耐震基準をクリアしている必要があります。注意したいのが、2000年5月31日以前に建築確認が行われた家で、たとえ新耐震基準で建てられていても、この等級には該当しないということです。
② 耐震等級2
耐震等級2は、耐震等級1に比べて1.25倍の耐震性があるとされています。耐力壁の筋交いの数を増やしたり、耐力壁の長さを調整したり、床の剛性を高めたりすることで、震度6~7の地震にも耐えられる構造になっています。そのため、万が一被害が発生した場合でも、補修を行えばその後も安心して住み続けることが可能です。
さらに、耐震等級2の認定を受けた家は、長期優良住宅としての認定を受けられるという点や、公共施設や避難場所としての役割を担う学校や病院も、耐震等級2以上が求められるという点からも、安全性の高さがわかります。
③ 耐震等級3
最高ランクである耐震等級3の建物は、大型地震に対する優れた安全性が特徴です。耐震性能は耐震等級1の1.5倍とされており、震度6~7の強い地震にも耐えるほどです。耐震等級3の住宅では、地震後も一部の軽微な修繕を行うだけで住み続けられるとされています。
消防署や警察署など、災害復興の拠点となる重要な建物では、耐震等級3の基準を満たすことが求められています。自然災害に直面しても倒壊や崩落のリスクを大幅に抑えられるため、安全な生活環境を作りたい場合には、耐震等級3の住宅を検討すると良いでしょう。
耐震等級が決まる4つのポイント
上記で解説した耐震等級は、建物の耐震性によって分類されていますが、具体的には以下4つの要素によって決まるといわれています。
- 建物の重さ
- 耐力壁の量
- 耐力壁や金物の配置
- 床の耐震性
これらの要素は、地震の揺れに耐えられる注文住宅を建てるために意識したいポイントなので、ここで学んでおきましょう。
① 建物の重さ
建物の耐震性能を左右する要素の1つ目は、建物自体の重さです。一般的に、建物が軽い方が耐震性は高まるとされています。
鉄骨造やコンクリート造の建物は重量があり、地震が発生すると大きく揺れるため、建物へのダメージも大きくなる傾向にあります。それに対して軽量な木造建築は、地震の揺れに対して振幅が小さく、建物にかかるダメージも抑えられる構造です。また、屋根の素材や建物の重さも、建物へのダメージの大きさに影響を与えます。
タイセーハウジングでは、木造の在来工法(軸組工法)と2×4工法(面工法)を取り入れた構造を採用しています。在来工法は、日本の伝統的な木造軸組工法を基にしたもので、間取りの自由度が優れている点が魅力です。2×4工法は、ツーバイ材を用いた木造壁式工法で、耐震性、防火性、断熱性が高いという特長を持っています。この2つの工法を掛け合わせることで、木造でも自然災害に強い高耐震構造の家作りを実現しています。
② 耐力壁の量
耐力壁の数が多ければ多いほど、建物の耐震性は高まります。耐力壁とは、地震や風などの横からの力に抵抗する壁であり、建物が水平力に耐えられるよう支える役割を持つものです。この壁は、建物の揺れを抑え、外部からの力を分散させる効果があるため、より地震に強い建物にするためには、多くの耐力壁を配置する必要があります。
③ 耐力壁や金物の配置
建物の耐震性を高めるためには、耐力壁の量だけでなく、配置バランスを考慮することも重要です。家の一部や片側に耐力壁が集中すると、地震発生時に弱い部分に過度な負荷がかかり、倒壊や崩落の危険性が増すためです。
タイセーハウジングでは、各建物に対して1棟ごとに200ページを超える許容応力度計算を行い、どこに面が必要となるのか、どの面を強化すべきかを、「軸」+「面」という観点から詳細に分析しています。
この構造計算を通じて、耐力面材を適切に配置し、壁全体で建物を支える構造を実現し、さらに、最新の金物で建物を補強することで、建物全体の耐震性を高めています。
④ 床の耐震性
耐震等級を考える際、家の構造として壁の強度に目が向きがちですが、実は床の耐震性も非常に重要です。
いくら壁の強度を高めたとしても、それを支える床の強度が不十分であれば、地震の揺れに耐えることはできません。もし床の剛性が低く、簡単にねじれたりひび割れたりするような状態であれば、壁は倒れたり、破損したりする危険性が高まります。そのため、床の強度を高めるための工夫も必要不可欠です。
タイセーハウジングでは、構造体と24mm厚の構造用合板を一体化させた剛床工法を採用。水平構面の剛性を確保し、強い耐震性を実現しています。
構造や性能に関する詳細はこちらをご覧ください
耐震・免震・制震の違い

建物の耐震性に関連する言葉で、「耐震」「免震」「制振」というワードを目にしたことがあるものの、どのような違いがあるかを知らないという方もいるでしょう。住宅の耐震性能について考える際に重要な知識ですので、ここで押さえておきましょう。
① 耐震
耐震は、地震による揺れに耐えられるよう建物自体を強化する仕組みです。地震が発生すると「地震力」と呼ばれる横からの強い力が建物に加わり、特に重量のある床や屋根に影響を与えます。そのため、柱や梁といった支柱を補強し、建物全体の強度を高めることが必要です。
壁に筋かいを入れる他、部材の接合部を金具で補強し、全体的に強度を高める方法が一般的で、一戸建て住宅や学校などさまざまな建物で広く採用されています。
② 免震
免震は、地震の揺れが直接建物に伝わりにくくする仕組みで、建物と地盤の間に「免震装置」を設置し、揺れを吸収して建物へのダメージを軽減するというものです。
免震装置は、揺れを吸収するダンパーやゴム状のアイソレータなどから構成されており、建物内部の損傷や家具の転倒といった二次被害を防いでくれます。
免震は耐震や制震に比べ、より強い地震にも対応できる点がメリット。しかし、導入コストが高いため、主にマンションで採用されるケースが多く、戸建てにおける導入数は少ないです。
③ 制震
制震は、地震の揺れを吸収して建物にかかる負荷を軽減する構造です。
建物内部に設置した制震ダンパーが揺れを熱エネルギーに変換し、高層ビルやタワーマンションなどの上階で発生する揺れを抑えるため、地震時でも比較的安定した環境を保てます。
免震構造と異なり、建物と地面が直接接しているため施工が容易で、コストも抑えられるのが特長です。一方で、装置の設置場所や数により効果が異なるため、建物の構造や使用用途に合わせて設計する必要があります。
耐震等級3の認定を受けるメリット
注文住宅を建てる際、最高レベルの耐震性である耐震等級3の認証を受けることにはいくつもの利点があります。ここでは特に注目すべき4つのメリットに絞ってご紹介します。
① 大きな地震でも損害が少ない
注文住宅で耐震等級3の認定を受ける最大のメリットは、耐震等級1や2の家と比較して、地震によって受けるダメージが少ないことです。
震度6強の地震が発生した場合、耐震等級1の家では倒壊や崩落を防げても、建物の損傷が大きい場合には建て替えが必要になる可能性があります。
一方、耐震等級3の家であれば損傷を小さく抑えられるため、大きな破損が発生して住み続けられなくなる心配は軽減されるといえます。
② 地震保険料の割引が受けられる
地震保険には「耐震等級割引」が設けられており、耐震等級が高いほど保険料が減額されます。
耐震等級1の場合は10%、耐震等級2で30%の割引が受けられるのに対し、耐震等級3では50%もの大幅な割引が適用されます。これは、過去に大地震が発生した際、耐震等級3の住宅が被害に遭いにくかったことから生まれた制度です。
なお、住宅を購入する際には火災保険への加入が必須ですが、火災保険では地震による火災などの被害は補償されません。地震保険の加入は任意とされていますが、地震に対して備えるのであれば、地震保険にも併せて加入することをおすすめします。
③ 住宅ローンの金利優遇を利用できる
住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用することで、住宅ローンの金利優遇を受けられる点も、耐震等級3を取得するメリットの1つです。
耐震等級3の住宅であれば、【フラット35】Sの金利Aプランを利用でき、当初5年の間は0.5%の金利優遇を受けられます。
この金利引き下げメニューは、2024年11月現時点で2025年3月31日までの申し込み分が対象で、かつ予算金額に達する見込みになると受付が締め切られるため、早めに検討するのがおすすめです。
④ 資産価値が高くなる
耐震等級3の認定を受けた家は、耐震性の高さが証明されているため、資産価値が高くなる傾向があります。これは、耐震等級3の家は地震によって損傷しにくく、地震発生後の売却でも建物の状態に問題がない可能性が高いことが理由です。
また「安心して暮らせる家」というイメージが売却時に有利に働くケースも多く、高く、かつ早く売却できる可能性も高いといます。
耐震等級3は必要?知っておきたいデメリットや注意点
暮らしの安全を守ってくれる耐震等級3ですが、注文住宅で耐震等級3の認定を受ける前に、知っておきたいデメリットや注意点もあります。場合によっては耐震等級2でも、希望の住まいが実現する可能性もあるため、慎重に検討しましょう。
① 建築費用が高くなる
耐震等級を高めると、それに比例して耐力壁の増設や金物を使用する必要があります。工事に伴う材料費や工事費が高くなるため、初期投資が大きくなることを理解しておきましょう。
さらに、耐震等級3の認定を受けるためには、約20万~40万円の申請費用が必要なのに加え、第三者評価機関による調査を受けなければなりません。
設計に通常5~6カ月、工事に6カ月を要するところ、耐震等級3の場合は各1カ月の延長が見込まれ、合計で約2カ月の遅延が発生する可能性があります。この間、現在住んでいる場所の仮住まいの家賃もかさむため、予算の見直しは必須です。
② 間取りや広さに制限が出る可能性がある
耐震等級3の住宅を考える際には、間取りや広さに制限が出る可能性があります。耐震性を高めるためには、適切な数の耐力壁を適切な場所に配置しなければならないため、広い空間を確保することが難しくなることがあるのです。
このような場合、タイセーハウジングではご希望の間取りを優先し、耐震等級2を提案する場合もあります。土地の形や広さ、間取りにもよりますが、耐震等級2の住宅でも、性能表示計算に基づけば、耐震等級3と同じかそれ以上の耐震性能を持つ住宅を建てることも可能です。
③ 100%倒壊や破損を防げるわけではない
耐震等級3を取得することで、耐震性能が大幅に向上し、耐震等級1や2に比べて大きなダメージを避けられる可能性は高くなります。しかし、どのような地震に対しても必ず倒壊や破損を防げるわけではありません。
自然災害は予測不可能な要素が多く、必ずしも100%の安全性を保証するものではないことを理解しておくことが重要です。それでも耐震等級3を取得することは、より安心な家だという指標となります。
④ 設計前に取得することを依頼する
注文住宅で耐震等級3を希望する場合、設計段階でハウスメーカーや工務店に、「耐震等級3の認定を受けたい」と明確に伝える必要があります。これは、耐震等級の認定は義務ではなく任意の制度のため、家を建ててからの変更はできないことが理由です。
また、耐震等級3の住宅は、建築費用がかさむだけでなく、間取りにも制約が生じる場合があります。そのため、本当に耐震等級3が必要かどうか、ハウスメーカーや工務店の担当者とじっくりと相談して判断することをおすすめします。
⑤ 「耐震等級3相当」とは異なる
ハウスメーカーの広告で「耐震等級3相当」という表現を見かけたことがある方もいるかもしれません。「耐震等級3相当」というのは耐震等級3と同等程度の耐震性を持つものの、第三者機関からの認定は受けていないということを意味しています。
認定を受けない分、住宅取得時の初期費用は抑えられるでしょう。しかし認定を受けていないということは、地震保険料の割引や住宅ローンの金利優遇といったメリットが受けられないということでもあります。
長い目で見たときに、将来的なコスト面での負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
⑥ 土地の地盤も重要
耐震等級3の住宅を建てる際、建物の強さだけでなく、土地の地盤にもこだわる必要があります。地盤が弱い場合、地震が発生した際に地盤沈下などが起きる可能性があります。たとえ耐震性能の高い住宅を選んでも、地盤が不安定であれば、せっかくの家も危険にさらされてしまうということです。
タイセーハウジングでは、土地探しからアフターメンテナンスまでワントップでサポートしています。土地から探している方は、ぜひ建物だけでなく、土地探しについてもご相談ください。土地と建物の両面から、安心して暮らせる住まい作りをサポートいたします。
注文住宅を依頼する会社選びのポイントは「構造計算」
耐震性の高い注文住宅を建て、安心して暮らせる住まいを実現するためには、ハウスメーカーや工務店選びが重要です。高い耐震等級に対応していて、独自の技術を持つ企業であれば、希望に合った間取りと耐震性能の高さを両立できる可能性が高いでしょう。
また、構造計算をしっかり行っているかどうかも、業者選びの大切な基準の一つです。構造計算とは、建物が大地震や台風、さらにはハリケーンなどの自然災害に耐えうるかを、さまざまな角度から科学的に検証することを指します。構造計算は3階建ての建物に関しては義務化されていますが、平屋建てや2階建てについては構造計算を行わないのが一般的です。そのため、木造住宅では構造計算がしっかりと行われていないケースも少なくありません。
タイセーハウジングでは、全棟において構造計算(許容応力度計算)を実施しており、地震に強く、長く安全に暮らせる住まい作りに注力しています。もしこれからハウスメーカーや工務店を選ぶという場合は、構造計算を確実に行っているかを問い合わせてみることをおすすめします。
耐震性が高く住み心地のよい家を建てよう
安全で快適な住まいを実現するためには、耐震性の高い家作りが重要です。
タイセーハウジングでは、一棟一棟に丁寧に向き合い、耐震性と住み心地を両立した住まいを提案しています。木造の在来工法と2×4工法を掛け合わせ、自然災害に強い高耐震構造を実現し、安心して暮らせる家を提供。また、許容応力度計算を全棟で実施し、建物全体の耐震性を徹底して強化しています。
ご家族の安全と安心を重視した住まい作りにご興味がありましたら、ぜひ資料請求をご検討ください。